第一章 アニメから始まった宇宙の旅
私が『プラネテス』に出会ったのは、漫画ではなくアニメ版からだった。2003年の放送当時、すでに「宇宙もの」として評判を聞いていた。そして第一回放送のスペースデブリを流れ星にするクルーの粋な配慮と船外活動のせこい手当の取得、一気にそのまま引き込まれた。
正直なところ、最初は「宇宙でゴミ拾い?」という印象だった。だが、その“ゴミ”にこそ人間の夢と矛盾が凝縮されていることに気づくのに、そう時間はかからなかった。
地球の軌道上を漂うデブリを回収する作業――そこに夢と人生を懸ける主人公・ハチマキや訳有気なくせの強い仲間たち。大志を抱きながらも、現実の中で小さく削られていくタナベの姿は、若いころの私には理解できなかった。
だが今、社会人として働く身になって振り返ると、この作品が描いていた「夢と妥協」「理想と現実の落差」の痛みが、ようやく自分の言葉で理解できるようになっている。
第二章 ユーリの喪失と救い ― “コンパス”という象徴
数あるエピソードの中で、私に最も深く刻まれたのはユーリの物語だった。ユーリは事故で妻を失い、宇宙に散った彼女の形見である小さなコンパスを探し続けている。
宇宙空間という果てのない虚無の中で、彼が握りしめていたのは愛する人とのつながりだった。
ある日、デブリ回収中に偶然そのコンパスを見つけるシーン。無重力の静寂の中で、彼は涙を流すでもなく、ただ小さく笑う。その瞬間、失われた時間が、ようやく癒やされていくように見えた。そこでデブリの海にぶつかり命からがら助けた仲間の姿は今でも覚えている。
この“コンパス”は、単なる小道具ではない。方向を指し示すはずのものが、喪失の象徴となり、やがて再生の象徴に変わる。その構造が美しい。
漫画版では第一話、(確か)アニメ版では数話目でだったと記憶している。
第三章 ユーリと九太郎 ― 宇宙という職場に生きる人間たち
もうひとつ、私が特に好きなのは、ハチマキと九太郎の関係である。九太郎は一見飄々としていて、どこか軽い。近いような遠いような師弟関係とも違うユーリとの関係。
ユーリは何か九太郎に眠っていた情熱や「託す」という思いが砂浜の一件で蘇ったのだろう。
ロケットの打ち上げがうまくいった時にユーリが前を(未来を)向き始めたのは、とてもうれしくもあった。そして自分は大人になった時に同じように導く、託すことができるような技術者になろうと思った。
20年越しでここで書くことではないが、あえて書こう。
九太郎
コンパスを壊してくれてありがとう。
第四章 夢と妥協の狭間で ― ハチマキの選択
ハチマキの夢は「自分の船を手に入れること」だった。だが物語の終盤、彼は木星探査船「フォン・ブラウン号」の乗組員となる。若いころの私は、そこに少し失望した。
言ってることが違うし、手に入れるってメンバーに入るだけだろ?
だが、年を重ね、現実の社会で働くようになってからは、この選択の意味が少しずつわかってきた。夢とは、必ずしも「自分のもの」を持つことではない。むしろ「どこかの一部として働きながら、自分の理想を少しでも実現すること」なのだと気づく。
宇宙の闇から放り出されたあの瞬間から、ハチマキは夢と現実に追い込む自分と向き合ったのだ。
第五章 ハキムというもう一つの“理想”
アニメ版で印象的なのが、ハキムという人物の描かれ方だ。
彼は地球の貧困地域出身で、宇宙開発の格差構造に怒りを抱いている。テロリストとしての道を選び、やがて破滅へと向かう。
漫画版ではここまで政治的な描写は少ないが、アニメ版では“理想を極端に押し進めた男”として強い存在感を放つ。理想のためなら恋人(のふりをしていたのかもしれないが・・)を利用する。
そして何よりも印象的なのは、彼が最期にルナリアンの少女との邂逅で「テロを辞める」ような暗示を残すことだ。完全な悪にはならない。理想を持ったがゆえに狂い、しかし最後にはその理想の重さに気づく――その人間らしさが胸を打つ。
ハキムの姿は、ハチマキの対極にある。
ハチマキが現実を受け入れた“成熟”を象徴するなら、ハキムは理想を手放せない“純粋さ”の残滓だ。
この二人の対比は、現実社会における“行動する理想主義者”と“折り合う現実主義者”の関係にも重なる。
第六章 “VHS”に残る宇宙 ― 時間を超える記録媒体
私の実家には、まだ『プラネテス』のアニメを録画したVHSテープが残っている。
再生機はもう半ば壊れかけており、映像はノイズ混じりだ。それでも、実家に帰るたびについ電源を入れてしまう。
画面の端に走る縦線や、かすれる音声。それらがむしろ懐かしく、作品の時代感をより強く思い出させてくれる。
宇宙の“デブリ”を描いた作品を、今や“映像デブリ”のような古いメディアで見ている――その構図が、何とも皮肉で、愛おしい。紙の漫画と同じように、物理的な媒体には“重み”がある。
電子書籍ではなく、紙で読む『プラネテス』。VHSで見る『プラネテス』。
その触感こそが、私にとっての“原体験”であり、私と作品との絆だ。
第七章 宇宙を舞台にした“地上の物語”
『プラネテス』は宇宙を描いているが、実際のテーマは人間社会そのものだ。
組織の中での摩擦、夢のすり減り、格差、孤独、そして希望――これらは宇宙に限らず、どんな職場にも存在する。 宇宙服を着ていようが、スーツを着ていようが、人は結局“生き方”で悩み続ける生き物なのだ。
アニメの脚本・監督陣がこの点を明確に意識していたことは、随所に表れている。宇宙を描くのではなく、“宇宙に生きる人間”を描く。
その結果、『プラネテス』はSFでありながら社会劇であり、同時に青春ドラマでもある。
どの立場で見ても、何かしら自分に重なる部分がある――それがこの作品の普遍性だ。
第八章 再読と再視聴のたびに深まる“成熟”
年を重ねるごとに、『プラネテス』は違って見える。
学生の頃はハチマキの夢に共感し、社会人になってからは彼の苦悩に共感する。
さらに歳を取ると、ユーリの静かな悲しみに寄り添えるようになる。
一つの作品の中で、年齢ごとに共感する登場人物が変わっていく――それが『プラネテス』の凄さだ。
漫画を紙で読み返すたび、あのページの匂いとともに、自分の人生の時間も思い出す。
アニメをVHSで再生するとき、ブランクノイズの向こうに、かつての自分の理想がかすかに見える。
『プラネテス』は、私にとって「過去の自分を映す鏡」であり、今でも新しい問いを投げかけてくる作品だ
第九章 宇宙という比喩 ― 現実を生きる勇気
結局のところ、『プラネテス』が描いていたのは「宇宙に行くこと」ではなく、「現実を生き抜くこと」だった。
宇宙の果てを目指すよりも、自分の足元を見つめること。 理想を追うよりも、いま隣にいる仲間を信じること。それが、ハチマキたちが最後に到達した“答え”なのだろう。
そしてこの作品を通して、私自身も学んだ。夢は変質してもいい。理想は現実とぶつかりながら、形を変えていく。だが、それを諦めとは呼ばない。
むしろ“成長”と呼ぶべきなのだ。ユーリが拾い上げたコンパスのように、私たちもそれぞれの方向を探し続けている。
そして時に、その方向が変わってもいいのだ。大切なのは進み続けること――その一点だけだ。
終章 “宇宙の塵”に宿る人間の尊厳
『プラネテス』という作品の核心は、「人間賛歌」にある。
社会の中で働き、疲れ、迷い、それでも明日へ向かう。
その繰り返しこそが、私たち一人ひとりの“宇宙活動”なのかもしれない。
『プラネテス』を語るとき、私はいつも静かな感謝の気持ちになる。
あのVHSの映像がいつか完全に再生できなくなっても、あの紙のページが擦り切れても、
私の中には確かに“宇宙の欠片”として、この作品が残り続けるだろう。
――夢を見て、夢に破れて、現実を見て、現実に生きて、それでも空を見上げ続ける。
それが、『プラネテス』が私に教えてくれた生き方である。

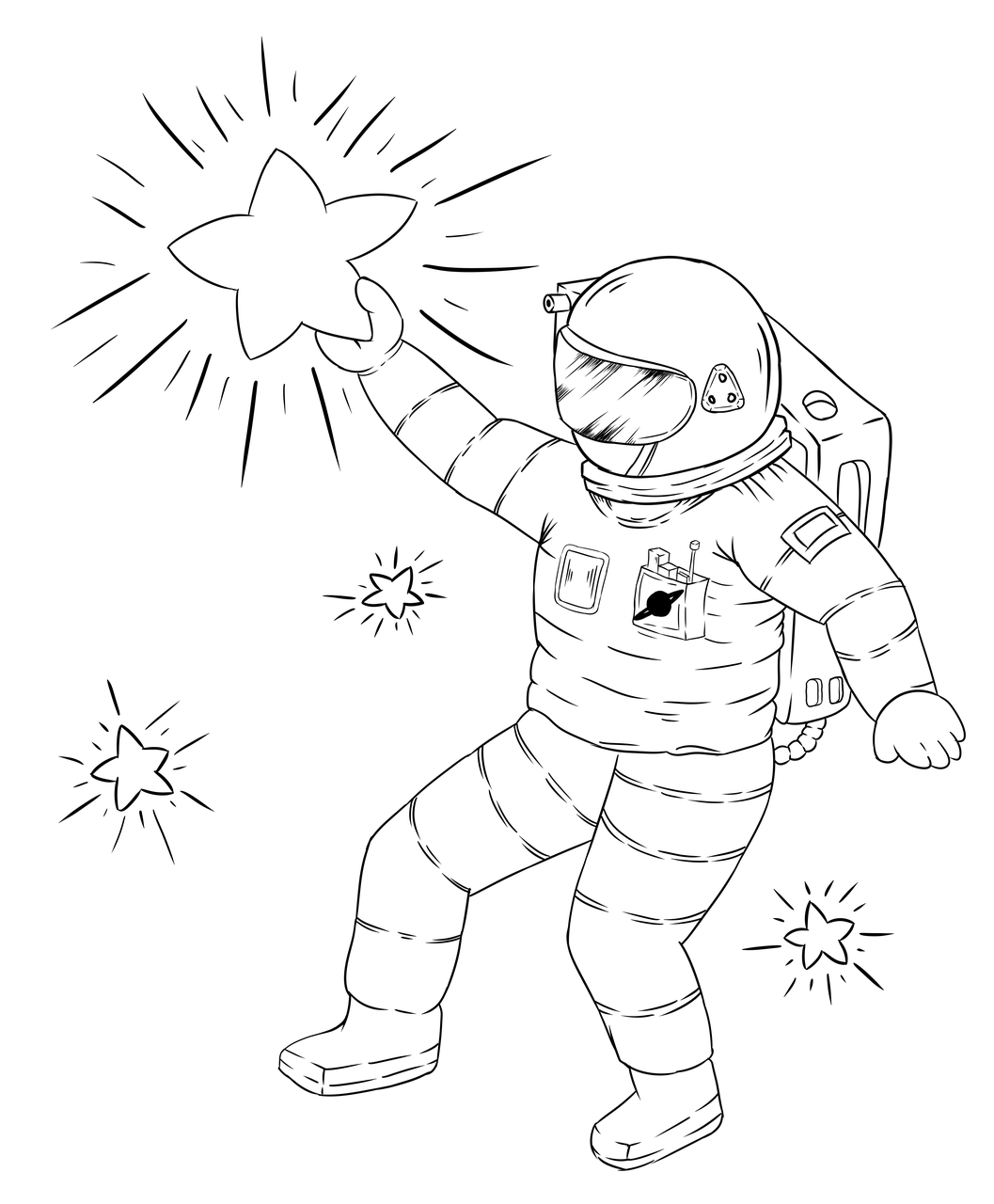


コメント